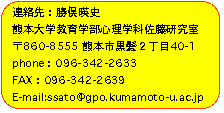小副川幸孝 1993 翻って生きよ:希望を生きる 新教社
小此木啓吾 1975 「希望」の心理:その精神分析的なとらえ方 児童心理,29, 888-893.
鑪幹八郎 1975 子どもの「未来への信頼」を育てるもの 児童心理,29, 779-786.
Snyder,C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S.A., Irving,L.M., Sigmon,S.T.,
![]()
勝俣 暎史(駒澤大学文学部教授 臨床心理学)
http://www.komazawa-u.ac.jp/~katsu/hope.html
1.ギリシャ神話及び聖書における「希望」
希望の重要性は古くから認識されている.西欧文化においては,「希望」の概念は前8世紀の詩人ヘシオドスが伝えるギリシャ神話の「パンドラの物語」に起源をもっていると言われている.また,「希望」は聖書の最も重要な教えである「信仰」「愛」「希望」の一つである.
1) ギリシャ神話における希望(パンドラの箱)
プロメテウス兄弟が天上の火を盗んで人間に与えたとき,怒ったゼウスは,その罪を罰するために初めて女というものを造ってプロメテウス兄弟と人間に贈ったという.初めて造られた女はパンドラと名づけられた.パンドラは天上で造られ,神々から様々な贈り物を与えられた.アプロディテは美を,ヘルメスは勧誘を,アポロンは音楽を,というように.こうしていろんな物がそろった上で,パンドラは地上に下されて,プロメテウスの弟のエピメテウスに与えられた.エピメテウスはプロメテウスに,ゼウスとその贈り物には注意しなければいけないと忠告されたけれども,それでも悦んでパンドラを受け取った.そのとき彼女は神々からのみやげとして1個の壷(いわゆる<パンドラの箱>)を持参していた.ゼウスからは「絶対に蓋を開けないように」と言われていたが,その忠告はゼウスの策の一つであった.好奇心にかられた彼女が蓋を開けると,嫉妬,憎悪,復讐などのおびただしい禍が飛び出して,人間の世界の隅々まで広く散った.パンドラは急いで蓋を閉じようとしたが,そのときにはもう間に合わなかった.壷の中の物はことごとく逃げ失せてしまったのである.壷の底の方に残ったものが一つあった.それは「希望」であった.
2) 聖書における「希望」
(1)「そればかりでなく,苦難をも誇りとします.わたしたちは知っているのです.苦難は忍耐を,忍耐は練達を,練達は希望を生むということを.希望はわたしたちを欺くことがありません」(ローマの信徒への手紙,5章3〜5節).
(2)「愛には偽りがあってはなりません.悪を憎み,善から離れず,兄弟愛をもって互いに愛し,尊敬をもって互いに相手を優れた者と思いなさい.怠らず励み,霊に燃えて,主に仕えなさい.希望をもって喜び,苦難を耐え忍び,たゆまず祈りなさい」(ローマの信徒への手紙,12章9〜12節).
(3)「それゆえ,信仰と,希望と,愛,この三つは,いつまでも残る.その中で最も大いなるものは,愛である」(コリントの信徒への手紙,14章13節).
「信仰」「希望」「愛」は,キリスト教の中心的な教えであると言われている.小副川(1993)は,「希望というのは,私たちの手持ちのものの延長にある期待とは全く違うものである.希望というのは,たとえば,どうにもならない現実と自分を,丸ごと,ヨシといって抱えて,歩き出すようなものである.聖書は,そのような生の在り方を”希望を生きる”とよんでいる」「忍耐は希望を生み出し,希望は失望に終わらない」と解説している.
2.辞書における「希望」の概念
「希望」という語は,日本語では,・「こいねがうこと.あることが実現することを待ち望むこと.また,その気持ち.のぞみ.願望」,・「将来への明るい見通し.のぞみ.可能性.見込み」(日本語大辞典)と定義されている.また,英語の「ホウプ」(hope) は,・「望ましい何かに対する願望 desire で,達成されるであろうという期待 expectation を伴ったもの,あるいはそれが達成されるという信念 belief」,・「上記の願望ないし信念の対象」,・「ある未来のできごとにおいての確信 confidence」(Webster)と定義されている.多少の表現上の相違はあるが,両者に共通しているのは,「将来ないし未来において,望ましい何かが実現ないし達成せられることについての確信(または,願望および信念)であって,期待を伴ったもの」ということではないかと解釈される.
3.心理学の領域での「希望」の定義
心理学の辞典の中には,「希望」あるいは「ホウプ」(hope) という用語は掲載されていない.現在の時点では,希望という概念は,心理学の重要な用語とはなっていないことを物語っているであろう.しかし,心理学の領域でも,希望の概念を重視した研究がないわけではない.そこで,筆者が入手し得た範囲内で,諸説(非精神分析的立場と精神分析的立場に立つものとに大別される)を紹介しておくことにしたい.
1)非精神分析的定義
(1)期待の延長線上に希望を位置づける立場
● レヴィン(Lewin, K.,1942)は,希望を未来の時間的展望の中に位置づけている.そして,希望とは「そのうちいつかは,こんな状態が変わって自分の望み通りになることもあるだろうということを意味し,個人の期待の水準と願望の水準とが似ていることを意味している」と定義づけている.また,心理学的未来は「時間的展望」の一部であるが,心理学的未来は「希望」と「絶望」との間をしばしば動揺すると述べている.
● ファーバー(Farber, M.L., 1968) は,希望は,「ある望まれた結果が起こるであろうという自信に満ちた期待を伴うものである」と定義し,希望の対象や希望の強さの水準は,人の行動の中核的な決定因子であるとしている.その場合,希望の対象は,おいしい食事が食べられることを期待しているときのように狭いこともあるし,人の全生涯にわたる広い焦点の希望であることもある.自殺が生じるのは,人生の見通し(広い焦点の希望)が絶望的な場合であるとした.
● ストットランド(Stotland, E.,1969)は,彼の著「希望の心理学」の中で,希望を「目標達成 goal attainment についての期待 expectation である」とした後,「希望のあること(有望性 hopefulness)は高い期待を意味し,希望がないこと(絶望 hopelessness)は低い成功の期待を指す」と述べている.彼はまた,希望の中核的変数として,目標達成についての認知された「可能性」と目標達成についての認知された「重要性」についても言及している.
以上に述べたレヴィン,ファーバーおよびストットランドらは,希望の定義づけに際して「期待」という概念を用いており,しかも,希望と期待との間に必ずしも明確な区別をしていないという点で共通している.
(2)希望と期待とを明確に区別する立場
一方,希望と期待とを明確に区別すべきであるとする立場の主なものとしては,レルシュ,メゾンヌーヴおよび北村らの定義が挙げられる.
● レルシュは希望を定義的に規定してはいないが,希望を「人生の価値や意義あるいは実現される視界または境域としての未来に向けられた動的な感情で,未来愛ともいうべきものである」とし,「希望と期待とはともに未来を志向するものであるが,希望というときには,目標となるものが明確なものとして設定されていないのに対して,期待ではその点がはっきりしている」と述べている(北村晴朗,1983).
● メゾンヌーヴも,希望は特定の対象をもたないで,いわば無条件に希望し,運命の意志にまかせるという信頼と一種の慎みや忍耐あるいは謙虚さをもつものである,としている.
● 北村晴朗(1983)は,希望に関する諸説および辞書的定義の検討を通して,希望を次のように定義づけている.彼によると,「希望は来るべき未来の状況に明るさがあるという感知に伴う快調をおびた感情である.希望は特定の目的の実現や,特定の目標の到達をめざすものではないが,人生の特定されない価値や意義が実現される視界または境域としての未来が信頼できるという明るい感情である」としている.明るい未来または未来の明るさについての快調をおびた感情であるという側面を強調している.
(3)総合的概念
● 勝俣暎史(1993)は,希望とは,「将来ないし未来において,望ましい何かが実現ないし達成されることをこいねがい,望むことであって,期望(期待して望むこと),祈望(祈り願うこと.強く願望すること),企望(企てその達成を望むこと),冀望(願い望むこと)を包含するものである」とし,欧米にはみられない漢字文化圏内における「希望」の概念の多様性を指摘している.
2)精神分析的定義
この立場に立つ代表的なものとして,エリクソンの定義が挙げられる.
● エリクソン(Erikson,E.,1964)によると,望み(希望)とは,「求めるものが得られるという確固とした信念である.たとえ存在の源初において,衝動や憎しみや暗闇に覆われているとしても」と定義づけ,望みは,「信頼できる母なる人物との最初の出会いにその萌芽をやどす」としている.小此木啓吾や鑪幹八郎らもエリクソンの立場を支持している(児童心理,第29巻第5号,1975).
エリクソンの希望に関する定義では,希望ないし望みの源は母親への基本的信頼と自己自身の同一性への基本的信頼にあることを強調している点にあると言える.すなわち,希望の萌芽は乳幼児期にあるというのである.
4.「希望」の構成成分
1)ファーバーの希望の公式
(1)希望の成分:希望を構成する成分(要素)について最初に提示したのは,ファーバー(Farber,M.L., 1968)であろう.彼は,希望は心理学の究極の分子ではなく,本質的にはパーソナリティ要因(有能感)と状況要因(脅威)との交互作用の結果であるとし,次の関数式を示した.
H = f ( C/T ) Hope(希望),function(関数)
Sense of Competence (有能感),Threat(脅威)
・希望(H)は有能感(C)の水準と正比例する.
・希望(H)は脅威(T)の水準と反比例する.
希望を維持したり,高めるためには,有能感の水準を維持ないし高めることが必要であるということである.逆に,有能感の水準が低下(萎縮)したり,脅威の水準が高まるならば,希望の水準は低下することを意味している.
(2)自殺の可能性と希望
ファーバーは,自殺と希望との関係を次の公式で示した.
S= f ( 1/H ) S= f( T/C ) Suicide (自殺の可能性)
●自殺の可能性(S)は希望(H)の水準と反比例する.換言すれば,自殺の可能性は,脅威(T)の水準と正比例し,有能感の水準(C)と反比例する.
2)希望の因子
●エリクソン(Erickson,R.C.,1975)─ 目標達成に関する期待
●ミラー(Miller,J.F.,1988)─ ・自己,他者および人生に関する満足の因子,・希望の脅かし回避因子,・未来についての予期因子
● スナイダー(Snyder, C.R.,1991) ─ ・発動性因子 agency(目標に関する決意),・通路因子pathways(障害を乗り越えて目標を達成する手段を見い出せる能力についての認知的評価)
●ベック(Beck,A.T.,1974)─ 絶望尺度(The 20-item Hopelessness Scale)・未来についての感情因子,・動機づけ喪失因子,・未来の期待因子
<文献>
Beck,A.T., Weissman,A., Lester,D., & Trexler,L. 1974 The measurement of pessimism: The hopelessness scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 861-865.
エリクソン E. /小此木啓吾(訳編)1974 自我同一性 誠信書房.
Erickson,R.C., Post,R.D., & Paige,A.B. 1975 Hope as a psychiatric variable. Journal of Clinical Psychology, 31, 324-340.
ファーバーM.L. 大原健士郎・勝俣暎史(訳)1977 自殺の理論 岩崎学術出版(Farber,M.L. 1968 Theory of suicide. New York: Funk & Wagnals)
ブルフィンチ/野上弥生子訳 1992 ギリシャ・ローマ神話 岩波書店
開田直幹 1990 希望をもって生きる 教育と医学,38, 302-308.
勝俣暎史 1990 希望の心理学 教育と医学,38,309-314.
勝俣暎史 1992 心理臨床における希望と有能感 熊本大学教育学部心理学科臨床心理学研究室未公刊資料,1-20.
勝俣暎史 1993 記憶療法の治療仮説 熊本大学教育学部紀要,42,人文科学,273-282.
小副川幸孝 1993 翻って生きよ:希望を生きる 新教社
小此木啓吾 1975 「希望」の心理:その精神分析的なとらえ方 児童心理,29, 888-893.
鑪幹八郎 1975 子どもの「未来への信頼」を育てるもの 児童心理,29, 779-786.
Snyder,C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Holleran, S.A., Irving,L.M., Sigmon,S.T.,
![]()